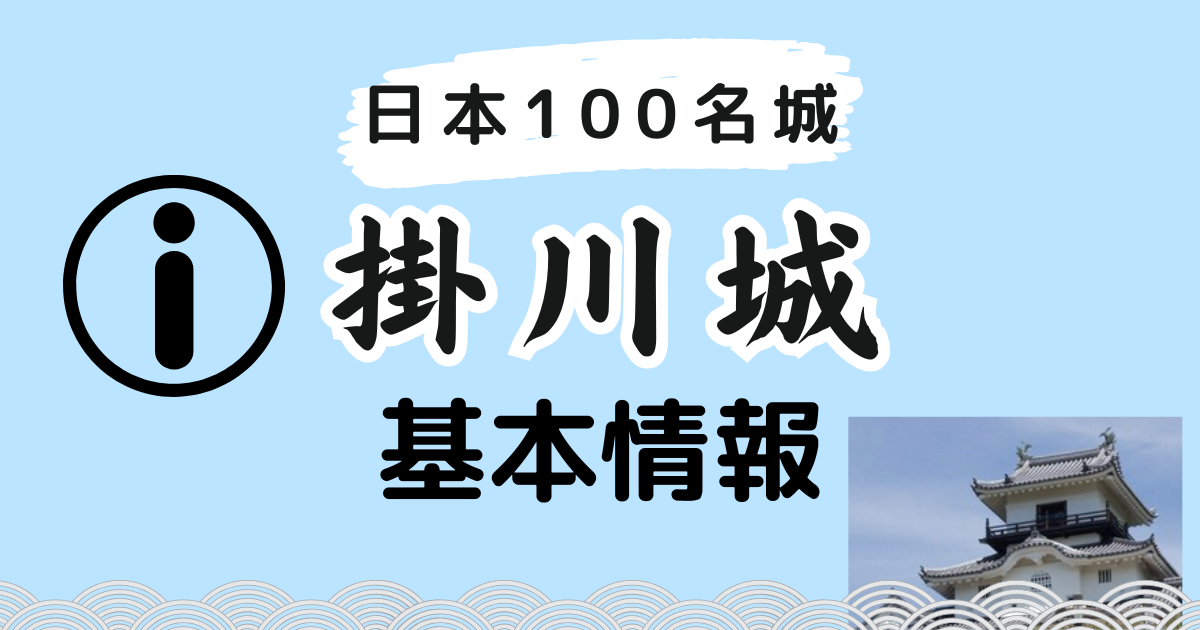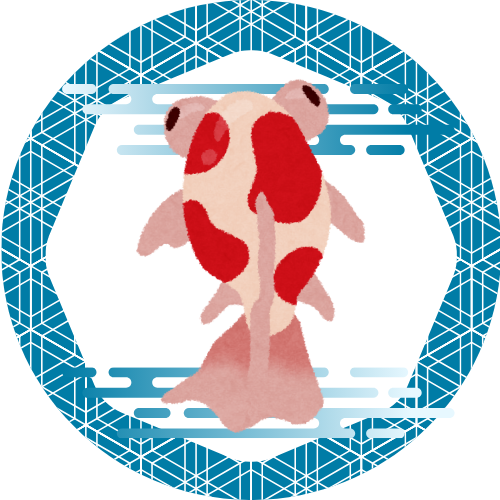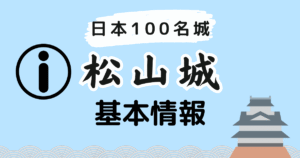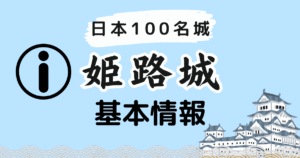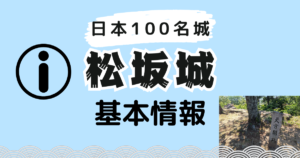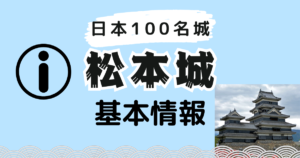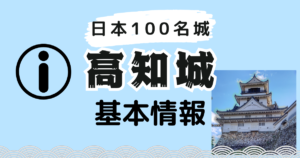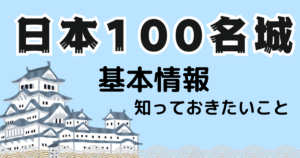こんにちは、ユーキです。
日本100名城に登録されている掛川城の基本情報をまとめました。
基本情報を押さえて、充実した訪問にしましょう。
基本情報
押さえておきたい基本情報をコンパクトにまとめました。
初代城主(最初に建てた人)
朝比奈泰煕(あさひなやすひろ)
来歴
室町時代に駿府の守護大名である今川義忠(いまがわよしただ)が遠江進出を狙い、部下である朝比奈泰煕(あさひなやすひろ)に築城を命じたのが始まりです。
当初は、子角山(ねずみやま:別名は龍胴山)に1497年(明応6年)から1501年(文亀元年)にかけて築城されました。これを「掛川古城」と呼びます。
現在の掛川城は、今川氏の勢力拡大により1513年(永正10年)、龍頭山に今川氏親によって築かれました。
1590年(天正18年)になると、山内一豊が掛川城に入城します。山内一豊は大規模な修築を行いました。
掛川城の天守はこの時、築かれたものになります。
1854年(嘉永7年・安政元年)の大地震によって天守が倒壊してしまいます。
再建されてのは1994年(平成6年)で、日本初の本格木造天守となりました。
再建にあたっては、山内一豊が築城した高知城を参考に、残された図面から復元されています。
見どころ
掛川城の見どころをまとめました。見たいところを事前にピックアップしておき、時間を有効に活用してください。
重要文化財
掛川城で国の重要文化財に指定されているのは、以下の1件です。
当時の姿を思い浮かべながら、見てみると楽しいかもしれません。
- 掛川城御殿
天守

日本初の「本格木造天守閣」として復元され、「東海の名城」とも呼ばれています。
外観3層、内部4層で、大きさも6間×5間(約12m×10m)とそれほど大きくはありません。
当時の山内一豊が作った天守は記録に残っていないため、詳細がわかっていません。そのため、復元にあたっては、似せて作ったといわれる高知城が参考にされています。
違いを比較してみるとおもしろいかもしれません。
掛川城御殿

国の重要文化財に指定されている、二の丸の御殿です。
城郭御殿が現存しているのは掛川城を含め、4か所しかありません。主要部分に含め、小書院や諸役所までほぼ全体が残っている非常に貴重な建物です。
1854年(嘉永7年・安政元年)の大地震で倒壊したものの、1855年(安政2年)から1861年(文久元年)にかけて再建された建物が現在にまで残っています。
掛川城御殿は藩の公的式典の場、城主の公邸、藩政の役所の3つの機能を持った施設です。当時の藩政や城主の生活に思いをはせることができるでしょう。
二の丸茶室

将棋好きの人はぜひ訪れてほしいです。
なぜならば、ここ二の丸茶室で、王将戦第一局が行われるからです。過去にここで対局した方々の書が展示されています。
入館すると、お茶(お菓子付)をいただくことができますので、休憩がてらに立ち寄りをお勧めします。
イベントなどが行われていなければ、対局で使われる部屋を見ることができます。
まとめ
掛川城の基本情報をまとめました。
- 掛川城を最初に建てたのは、朝比奈泰煕(あさひなやすひろ)
- 二の丸御殿が国の重要文化財に指定
- 見どころは重要文化財、天守、掛川城御殿、二の丸茶室
訪問の参考になれば、幸いです。